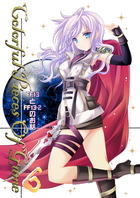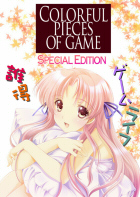2012-03-13 Tue [ ゲームについて::イロイロ ]
実は結構書いてから時間のたった文だったりする。
4gamerのダンガンロンパの記事を読んだとき、同人誌にちょろっとレビューに関する文を書いてから思っていたことが、一気に凝縮した感じで書き上げたのだけど、公開したからといって、別にだからどうしただよなあと思って放置してたのだけど、聞いてみたら、結構読みたい人がいるらしいのでアップすることにした。
馬鹿馬鹿しく長い文なので、3-4回ぐらいに分割してアップするつもり。
さて。話はここから始まる。
ゲームの評価ってなんだろう?――クリエイター魂が溢れ出る怪作「ダンガンロンパ」を遊びながら考えてみる
結構納得できる内容だったのだが、一つ「え?」と思ったのが、この一節。
海外だけでもないし、ここ最近でもない。
点数をつける形式のゲームのレビューの点数には、10点満点・100点満点・S-Eまでで表す…ともかく、さまざまな方法があるが、遥か遠い昔、コンソールゲームが登場したときから満点からの減点方式だったし、それ以外であったことはない。(ごくごくまれに点数のないレビューは存在したが、僕の記憶する限り、エッセイ以外の方法で、その手のレビューが長続きしたことはないと思う)。
そしてこの点数方式を取る限り、隙がない作りが高得点になるし、これは今のゲームにとって問題で、とても不幸なことだと思っている。
これはレビューをやめる前後から約10年ほど思っていたが、同人誌に一度書いただけで、本当に詳しく書いたことは一度もなかったのだけど、いい機会なので書いておきたい。
続きを読む▽
4gamerのダンガンロンパの記事を読んだとき、同人誌にちょろっとレビューに関する文を書いてから思っていたことが、一気に凝縮した感じで書き上げたのだけど、公開したからといって、別にだからどうしただよなあと思って放置してたのだけど、聞いてみたら、結構読みたい人がいるらしいのでアップすることにした。
馬鹿馬鹿しく長い文なので、3-4回ぐらいに分割してアップするつもり。
さて。話はここから始まる。
ゲームの評価ってなんだろう?――クリエイター魂が溢れ出る怪作「ダンガンロンパ」を遊びながら考えてみる
結構納得できる内容だったのだが、一つ「え?」と思ったのが、この一節。
ここから話は少し本作自体から離れるが,ここ数年,開発費数十億円,場合によっては100億円超というハリウッド映画クラスの大作ゲームが世界を席巻しているのはご存じの通り。それらのゲームは確かに凄いし面白いのだが,半面,それらを評価するゲームメディア(主に海外)の評価の仕方に,一抹の疑問を覚えることも少なくない。端的に言うと,
最上級のグラフィックス。隙のないゲームシステム……100点。
とか,そういう書き方のことなんだよね。なんと言うか,「隙がない作りなら,ゲームって面白いのかよ?」という至極まっとうな疑問が,筆者の頭の中で反芻されてしまうというか。ゲームって,エンターテイメントって,クリエイティブさって,そんな単純なものじゃないだろう。既存の表現手法の延長で隙無く完璧に作られたゲーム,それって本当にイコールで「最高のゲーム」になるものなんだろうか?
最上級のグラフィックス。隙のないゲームシステム……100点。
とか,そういう書き方のことなんだよね。なんと言うか,「隙がない作りなら,ゲームって面白いのかよ?」という至極まっとうな疑問が,筆者の頭の中で反芻されてしまうというか。ゲームって,エンターテイメントって,クリエイティブさって,そんな単純なものじゃないだろう。既存の表現手法の延長で隙無く完璧に作られたゲーム,それって本当にイコールで「最高のゲーム」になるものなんだろうか?
海外だけでもないし、ここ最近でもない。
点数をつける形式のゲームのレビューの点数には、10点満点・100点満点・S-Eまでで表す…ともかく、さまざまな方法があるが、遥か遠い昔、コンソールゲームが登場したときから満点からの減点方式だったし、それ以外であったことはない。(ごくごくまれに点数のないレビューは存在したが、僕の記憶する限り、エッセイ以外の方法で、その手のレビューが長続きしたことはないと思う)。
そしてこの点数方式を取る限り、隙がない作りが高得点になるし、これは今のゲームにとって問題で、とても不幸なことだと思っている。
これはレビューをやめる前後から約10年ほど思っていたが、同人誌に一度書いただけで、本当に詳しく書いたことは一度もなかったのだけど、いい機会なので書いておきたい。
書いておくと、僕はいわゆる「レビュワー」として、1988-1999年の間、PCエンジン・PS1のレビュワーをずっとやっていた。以降は、電撃PSのコラムで気が向いたらゲームのレビューを書くことはあるが「プロのレビュワー」として点数をつけたことはない。
また評価・評論という話になると、Beepからやってたわけで、だいたい1986年から今まで、ずっとゲームの(評価・評論という意味での)レビューをやっていることになる。
まあBeep時代のレビューは、僕の頭をぶん殴りたいぐらい腹が立つけれど。
また評価・評論という話になると、Beepからやってたわけで、だいたい1986年から今まで、ずっとゲームの(評価・評論という意味での)レビューをやっていることになる。
まあBeep時代のレビューは、僕の頭をぶん殴りたいぐらい腹が立つけれど。
続きを読む▽
|| 19:47 | comments (0) | trackback (x) | △ ||
2012-03-11 Sun [ 昔のこと::ハドソン関係 ]
書き上げたあと、自分的にとても気に入っているのと、やっぱブログで書いたのは構成が気に入らない…連載みたいなもので、あとからあーこうしたらとか、こんな事実が! みたいなのがあって、4月の終わりにあるコミックイチで本にしちゃおうと思って、現在、構成を組み立てなおしながら、資料なども追加しつつ、書いているところ。
で、書いてるうちにわかった細かいことなどを、ちょっとメモ書き代わりに残しておきたい。
1982年のX1での協力で、ハドソンではX1は安く買えたということだった。だから一時、ハドソンはX1だらけになっていたとのことだった。僕がハドソンにいった1988年にはもうX1は開発では使われていなくて、飛田さんとか一部人たちの机の上に残っていた程度だったので、さっぱりわからなかった。
X1でゲームを書き始めた最初の頃、本迫(もとさこと読む)さんが作ったX1用のBASICコンパイラがあり、それを使ってゲームを開発していたらしい。
らしいというのは、開発していた人たちはそう言っているのだけど、開発した当の本人であるはずの本迫さんに確認したところ全く覚えておらず「俺そんなことしたっけ!?」だったから、真偽が全く不明なのだ。
当時の数少ないハドソンのメンバーでこの真偽を覚えている人はいないだろうかw
ところがBASICコンパイラは当たり前のことながら、当時のコンパイラなのでランタイム(動かすときに必要なライブラリ)が大きい・コンパイル効率が悪くコードが大きい・速度が遅い(フルアセンブラより遅い)、案外他機種への移植が大変…といった問題があり、互換ライブラリを作ってフルアセンブラ(オールマシン語)の方向に話は進んだ、ということらしい。
それで、最初のフルアセンブラゲームがなんだったのかというとボンバーマン。
中本さんが1日で書いたのが最初だったと僕は聞いた。
単純なゲームだけど、それでも1日で書くってのはスゲエ…つってもライブラリは既に大量にあったろうから、1日でコア部分を書いたってことだろうけど。
当時の主流はZ80だったので、結局X1で書いたアセンブラのゲームを他のマシンへ移植するのは互換ライブラリがあれば楽だった、ということなのだろう(今で言うPS3/X360のマルチよりたぶん楽だったと思う)。
あとナッツ&ミルクとロードランナーの発売日が7/20説と、7/28&7/31で2説あるのについては確認が取れた。当時の流通の都合で3日ずれでばらけて発売されたように見えるけれど、ハドソンの公式な発売日は7/20だそうだ。
つまり、ロードランナーがナッツ&ミルクよりも後に見えるのは、当時の流通の都合でしかない、ということだ。
僕の想像だけど、当時は流通も小売も、今のように発売日を厳密に管理していなかったので、7/20に流通に出荷され、実際に売りに出されたのがナッツ&ミルクが7/28ごろ、ロードランナーが7/31になったということなのだろう。
かくして、ハドソンのファミコンデビュー作は同日発売になったのだった。
で、書いてるうちにわかった細かいことなどを、ちょっとメモ書き代わりに残しておきたい。
1982年のX1での協力で、ハドソンではX1は安く買えたということだった。だから一時、ハドソンはX1だらけになっていたとのことだった。僕がハドソンにいった1988年にはもうX1は開発では使われていなくて、飛田さんとか一部人たちの机の上に残っていた程度だったので、さっぱりわからなかった。
X1でゲームを書き始めた最初の頃、本迫(もとさこと読む)さんが作ったX1用のBASICコンパイラがあり、それを使ってゲームを開発していたらしい。
らしいというのは、開発していた人たちはそう言っているのだけど、開発した当の本人であるはずの本迫さんに確認したところ全く覚えておらず「俺そんなことしたっけ!?」だったから、真偽が全く不明なのだ。
当時の数少ないハドソンのメンバーでこの真偽を覚えている人はいないだろうかw
ところがBASICコンパイラは当たり前のことながら、当時のコンパイラなのでランタイム(動かすときに必要なライブラリ)が大きい・コンパイル効率が悪くコードが大きい・速度が遅い(フルアセンブラより遅い)、案外他機種への移植が大変…といった問題があり、互換ライブラリを作ってフルアセンブラ(オールマシン語)の方向に話は進んだ、ということらしい。
それで、最初のフルアセンブラゲームがなんだったのかというとボンバーマン。
中本さんが1日で書いたのが最初だったと僕は聞いた。
単純なゲームだけど、それでも1日で書くってのはスゲエ…つってもライブラリは既に大量にあったろうから、1日でコア部分を書いたってことだろうけど。
当時の主流はZ80だったので、結局X1で書いたアセンブラのゲームを他のマシンへ移植するのは互換ライブラリがあれば楽だった、ということなのだろう(今で言うPS3/X360のマルチよりたぶん楽だったと思う)。
あとナッツ&ミルクとロードランナーの発売日が7/20説と、7/28&7/31で2説あるのについては確認が取れた。当時の流通の都合で3日ずれでばらけて発売されたように見えるけれど、ハドソンの公式な発売日は7/20だそうだ。
つまり、ロードランナーがナッツ&ミルクよりも後に見えるのは、当時の流通の都合でしかない、ということだ。
僕の想像だけど、当時は流通も小売も、今のように発売日を厳密に管理していなかったので、7/20に流通に出荷され、実際に売りに出されたのがナッツ&ミルクが7/28ごろ、ロードランナーが7/31になったということなのだろう。
かくして、ハドソンのファミコンデビュー作は同日発売になったのだった。
2012-03-08 Thu [ 昔のこと ]
今日(3/8)、鶴見六百、つまり清水芋吉からツイッターで伝えられて、思わず少しつぶやいたけど、やっぱこういうことはブログとかに書いておこうと思ったので、日記がてらに、Beepから始まった、歴史としては日本最古と言っていいゲーム専門誌が休刊するということで、ちょっと思い出話などを書いておきたい。
僕が実質的にライターデビューしたのはBeepだった。
そして、Beepは僕の人生に決定的な影響を与えている。
どうして…という話を始めると複雑怪奇なのだけど、面倒くさい話をはしょって簡単にまとめると、僕が入社したベンチャー企業は漫画家の御厨さと美先生が関係していた。
そして御厨先生のプロダクションは当時ちょうどBeepの読者コーナーの仕事を請ける話になっていた。
これがYATATA WARS。
今で言う読者参加型ゲームの走りみたいなものだけど、当時はそこらへんをうまくシステム化できなくて、イマイチ盛り上がらなかったのは残念なところだ(読者コーナーとしては結構盛り上がった)。
僕はログインでゲームを出したことなどもあり「YATATA WARSの1コーナーとしてゲームプログラムを載せないか?」と言われたのが、ライター経歴の本格的なスタートだった。
そして僕のコーナーは、毎号プログラムを載せ、その解説を書くスタイルで始まったのだけど、これが結構人気があったらしく「ヤタタウォーズが終わった後も、コーナーは続けない?」といわれて、ヤタタウォーズが終了してからあとも、独立した連載コーナーとしてBeepの中で生き延びることになった。
こうして独立したコーナーになったのだけど、しばらくして「プログラムだけじゃなくて、ゲームのレビュー書いていいですかね?」と聞いたところ「どうぞ、どうぞ」というので、ちょっとゲームをレビューした。
そしたら、これがアンケートがよかったらしく、当時の担当から「ゲームのレビューの人気があるから、そっちを中心にしませんか」といわれ、ゲームのレビュー&評論コーナーになっていった。
それで、Beep!メガドライブになるまで、僕はBeepに書いていくことになったわけだ。
この偶然の積み重ねは続いていく。
1986年、ヤタタウォーズ(と、あと攻略本なんか)で知り合いの編集だったSKさんが、角川メディアオフィス(KMO)でマル勝ファミコンの立ち上げに関係することになった。そして、この関係で、86年の後半ぐらいからKMOで仕事をするようになる。
1987年に、そのSKさんから「ハドソンがゲーム作れるやつ探してるんだけど、企画しない?」といわれ、ハドソンに行って中本さんと会い、会社を辞めてゲーム屋になることを決める。
1988年に、ハドソンに行って、僕はゲームを作るプロの方に立つことになり、今にいたる筋道の決定的な線が引かれることになった。
もちろん1984年のBeepよりもずっと前から、この偶然の積み重ねは続いてる。
そして、88年よりあとにもやっぱりたくさんあって、そんな偶然の積み重ねばかりで僕の人生は出来上がっているけれど、それでも84年のBeepと88年のハドソンは、自分の人生を決定的に変えた大きなポイントに挙げる場所なのは間違いない。
そして人生の大きなポイントになったBeepとハドソンが、同じ年に似たタイミングでなくなることに、信じがたい不思議な運命を感じてしまうとともに、一時代の終わりをしみじみと感じているのだった。
僕が実質的にライターデビューしたのはBeepだった。
そして、Beepは僕の人生に決定的な影響を与えている。
どうして…という話を始めると複雑怪奇なのだけど、面倒くさい話をはしょって簡単にまとめると、僕が入社したベンチャー企業は漫画家の御厨さと美先生が関係していた。
そして御厨先生のプロダクションは当時ちょうどBeepの読者コーナーの仕事を請ける話になっていた。
これがYATATA WARS。
今で言う読者参加型ゲームの走りみたいなものだけど、当時はそこらへんをうまくシステム化できなくて、イマイチ盛り上がらなかったのは残念なところだ(読者コーナーとしては結構盛り上がった)。
僕はログインでゲームを出したことなどもあり「YATATA WARSの1コーナーとしてゲームプログラムを載せないか?」と言われたのが、ライター経歴の本格的なスタートだった。
そして僕のコーナーは、毎号プログラムを載せ、その解説を書くスタイルで始まったのだけど、これが結構人気があったらしく「ヤタタウォーズが終わった後も、コーナーは続けない?」といわれて、ヤタタウォーズが終了してからあとも、独立した連載コーナーとしてBeepの中で生き延びることになった。
こうして独立したコーナーになったのだけど、しばらくして「プログラムだけじゃなくて、ゲームのレビュー書いていいですかね?」と聞いたところ「どうぞ、どうぞ」というので、ちょっとゲームをレビューした。
そしたら、これがアンケートがよかったらしく、当時の担当から「ゲームのレビューの人気があるから、そっちを中心にしませんか」といわれ、ゲームのレビュー&評論コーナーになっていった。
それで、Beep!メガドライブになるまで、僕はBeepに書いていくことになったわけだ。
ところでBeepはライターがほとんど遊び感覚だったから、本当に面白くて、撮影するためにみんなで暗室でMSXのグラディウス2を一晩中攻略してたり、ロックマンやってハマりまくったり、芋吉が「1日一回、ファンタジーゾーン!」とか言いながら、クリアしてたり、誰だったか忘れたけど「ジェニージェニー」ってわめきながらプレイしてたり、全くどうかしてる編集部だった。
この偶然の積み重ねは続いていく。
1986年、ヤタタウォーズ(と、あと攻略本なんか)で知り合いの編集だったSKさんが、角川メディアオフィス(KMO)でマル勝ファミコンの立ち上げに関係することになった。そして、この関係で、86年の後半ぐらいからKMOで仕事をするようになる。
1987年に、そのSKさんから「ハドソンがゲーム作れるやつ探してるんだけど、企画しない?」といわれ、ハドソンに行って中本さんと会い、会社を辞めてゲーム屋になることを決める。
1988年に、ハドソンに行って、僕はゲームを作るプロの方に立つことになり、今にいたる筋道の決定的な線が引かれることになった。
もちろん1984年のBeepよりもずっと前から、この偶然の積み重ねは続いてる。
そして、88年よりあとにもやっぱりたくさんあって、そんな偶然の積み重ねばかりで僕の人生は出来上がっているけれど、それでも84年のBeepと88年のハドソンは、自分の人生を決定的に変えた大きなポイントに挙げる場所なのは間違いない。
そして人生の大きなポイントになったBeepとハドソンが、同じ年に似たタイミングでなくなることに、信じがたい不思議な運命を感じてしまうとともに、一時代の終わりをしみじみと感じているのだった。
2012-03-07 Wed [ 同人のコト ]
昔、そう12年ほど昔…2000年になる前後まで、僕はゲーム系の同人誌を作っていた。
たいていは「XXXなゲームライフ」みたいなタイトルでシリーズで作っていて5冊ほど出したところで、なんとなく作るのを止めて、10年ほど経って、また作り始めたわけだ。
どんな同人誌だったのかというと、たいていは力が入った、今読むと恥ずかしくなるようなゲーム論と、あとはアホっぽいゲームへのレビューが組み合わせになった本だった。
読むと恥ずかしくなるゲーム論は、教条主義的すぎて情けないだろうとか、エラソーに書きすぎだろうって感じなのだけど、今でも考え方の基礎はあんま変わってないので、このブログにいろんな形で出てきているので、まあ別に構わないのだけど、全くどこにも出ていないのがレビュー。
そりゃ当たり前で、10年以上昔のゲームのゲームのレビューだ。そんなもん、イマサラ出してどうするんだ? といいたくなるだろう。
で、その中に『センチメンタルグラフティ12人同時攻略』という、すこぶる下らないネタがあり、たまたまツイッターでつぶやいて、ブログに載せていると思っていたら載っていなかった。
まあ考えてみれば表は大量にいるし、めんどくさいし、だいたい需要もないだろうし、なにより結構長くて3-4回には分割しないといけないし、めんどくさい思って載せてなかったのだけど、読みたいという人が結構出てきて、しかも他のソフトについても読みたいという人が結構いるので、なら全部まとめなおして、電子書籍化して、300円ぐらいで出そう! というのが誰得ゲームライフだ。
まさに誰得な内容で、どこのだれが欲しいのかすらわからない代物だけど、だからこそ電子書籍だ。
タダでもいいのではないか? とも考えたけれど、やはりれっきとした仕事…じゃなくて趣味だけどw 時給計算したらマクドナルドでバイトするほうが賢いとしても、300円ぐらいはいただこうと思っている。
さて収録タイトルについては、いまさらタイトルを書いたところで、やったことすらない人が多いだろうということで、ゲームの解説などもいれつつ、現在の目から見た、アップデートされた内容にして出したいと思ってるw
ちなみに含まれるゲームは以下の通り。
ドラクエ7
DDR
影牢
やるドラ
みつめてナイト
センチメンタルグラフティ
まさに電子書籍以外では許されない極限のラインアップ。
こんなかでまともなのはドラクエとDDRだけだろ…w
たいていは「XXXなゲームライフ」みたいなタイトルでシリーズで作っていて5冊ほど出したところで、なんとなく作るのを止めて、10年ほど経って、また作り始めたわけだ。
どんな同人誌だったのかというと、たいていは力が入った、今読むと恥ずかしくなるようなゲーム論と、あとはアホっぽいゲームへのレビューが組み合わせになった本だった。
読むと恥ずかしくなるゲーム論は、教条主義的すぎて情けないだろうとか、エラソーに書きすぎだろうって感じなのだけど、今でも考え方の基礎はあんま変わってないので、このブログにいろんな形で出てきているので、まあ別に構わないのだけど、全くどこにも出ていないのがレビュー。
そりゃ当たり前で、10年以上昔のゲームのゲームのレビューだ。そんなもん、イマサラ出してどうするんだ? といいたくなるだろう。
で、その中に『センチメンタルグラフティ12人同時攻略』という、すこぶる下らないネタがあり、たまたまツイッターでつぶやいて、ブログに載せていると思っていたら載っていなかった。
まあ考えてみれば表は大量にいるし、めんどくさいし、だいたい需要もないだろうし、なにより結構長くて3-4回には分割しないといけないし、めんどくさい思って載せてなかったのだけど、読みたいという人が結構出てきて、しかも他のソフトについても読みたいという人が結構いるので、なら全部まとめなおして、電子書籍化して、300円ぐらいで出そう! というのが誰得ゲームライフだ。
まさに誰得な内容で、どこのだれが欲しいのかすらわからない代物だけど、だからこそ電子書籍だ。
タダでもいいのではないか? とも考えたけれど、やはりれっきとした仕事…じゃなくて趣味だけどw 時給計算したらマクドナルドでバイトするほうが賢いとしても、300円ぐらいはいただこうと思っている。
さて収録タイトルについては、いまさらタイトルを書いたところで、やったことすらない人が多いだろうということで、ゲームの解説などもいれつつ、現在の目から見た、アップデートされた内容にして出したいと思ってるw
ちなみに含まれるゲームは以下の通り。
ドラクエ7
DDR
影牢
やるドラ
みつめてナイト
センチメンタルグラフティ
まさに電子書籍以外では許されない極限のラインアップ。
こんなかでまともなのはドラクエとDDRだけだろ…w
2012-03-04 Sun [ 天外2製作メモ ]
間でハドソンのこと調べたり、いろんなことやってたらえらく間が空いてしまったけれど(;´ω`)
91年3月。(正確には1-3月の間なんだけど)いろいろ僕らは困りだしていた。
というのも、音楽…というか、作曲家がいつまで経っても決まらなかったからだ。
この頃には音楽に関する仕様は、もちろんほぼ固まっていた。
まず4人のテーマがあること。
これはもともと桝田さんか広井さんか、どっちかからのオーダーで始まった。タイトル以外に4人のキャラクターそれぞれのアニメーションデモを入れる仕様が決まったとき、ほぼ一緒に決まったことだった。
(この手のオーダーをするのは広井さんが多かったので、たぶん広井さんだと思うのだけど、自信はない)。
なんにしても4人のテーマがあると、それぞれの活躍する場面で曲を簡単に決められるメリットがあり、かつ分かりやすくて汎用性が高いから、僕は大賛成だった。
続きを読む▽
91年3月。(正確には1-3月の間なんだけど)いろいろ僕らは困りだしていた。
というのも、音楽…というか、作曲家がいつまで経っても決まらなかったからだ。
この頃には音楽に関する仕様は、もちろんほぼ固まっていた。
まず4人のテーマがあること。
これはもともと桝田さんか広井さんか、どっちかからのオーダーで始まった。タイトル以外に4人のキャラクターそれぞれのアニメーションデモを入れる仕様が決まったとき、ほぼ一緒に決まったことだった。
(この手のオーダーをするのは広井さんが多かったので、たぶん広井さんだと思うのだけど、自信はない)。
なんにしても4人のテーマがあると、それぞれの活躍する場面で曲を簡単に決められるメリットがあり、かつ分かりやすくて汎用性が高いから、僕は大賛成だった。
どうして4人のデモがあるかというと、広井さんは天外Ⅱを「キャラクタのゲームである」(キャラの立ったゲームであること、みたいな意味)と定義していた。
そして桝田さんはもちろんそれを忠実に敷衍しており、キャラクタを立たせるためならなんでもやる的なところがあり、これがまた「スーパーCDROMならデモでもこんなにスゴイ」的な宣伝戦略と組み合わさり、4人のアニメーションデモがある、ということに決まったのだ。
4人分デモ作るのはいいし贅沢だけど、スーパーCDとは関係ないよなあ…って当事思ってたw
そして桝田さんはもちろんそれを忠実に敷衍しており、キャラクタを立たせるためならなんでもやる的なところがあり、これがまた「スーパーCDROMならデモでもこんなにスゴイ」的な宣伝戦略と組み合わさり、4人のアニメーションデモがある、ということに決まったのだ。
4人分デモ作るのはいいし贅沢だけど、スーパーCDとは関係ないよなあ…って当事思ってたw
続きを読む▽