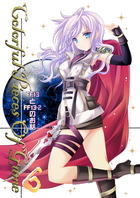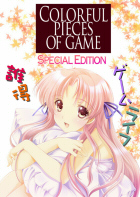2014-01-30 Thu [ 昔のこと ]
最近、エメラルドドラゴン(以下、エメドラ)のPCエンジン版が20周年だっと言われたので、ちょっと移植が始まった時の話をメモ代わりに簡単に。
もともと、エメドラを作る理由になったのは、当時結構騒ぎになった角川のお家騒動のせいだった。
お家騒動の件については、インターネットで検索でもしてもらえばいいのだけど、そのとき、角川メディアオフィスから飛び出たメンバーで創業されたのがメディアワークスで、そこに僕が参加してたゲーム事業部があった。で、なんにしても立ち上げた雑誌とタイアップで盛り上がれる目玉が欲しいというので、当時複雑だった権利関係をまとめあげられてスタートしたのが『エメラルドドラゴン』。
続きを読む▽
もともと、エメドラを作る理由になったのは、当時結構騒ぎになった角川のお家騒動のせいだった。
お家騒動の件については、インターネットで検索でもしてもらえばいいのだけど、そのとき、角川メディアオフィスから飛び出たメンバーで創業されたのがメディアワークスで、そこに僕が参加してたゲーム事業部があった。で、なんにしても立ち上げた雑誌とタイアップで盛り上がれる目玉が欲しいというので、当時複雑だった権利関係をまとめあげられてスタートしたのが『エメラルドドラゴン』。
ちなみに複雑怪奇だった権利関係を誰がまとめあげたのかはさっぱり知らないので、そこらへんを僕に聞かれても困る。あと、この権利が今ではどうなってるかもわからないので、リメイクとかできないんですかとか聞かれてもわからない。同じ理由で配信についてもわからない。
続きを読む▽
2014-01-27 Mon [ ゲーム作りライフ ]
突然だけど、これの続き。
僕が結構尊敬している論客の方々はグローバルリズムについての立場はイロイロなのだけど、その中でどうにも納得が行かない主張をなさる方々がおられる。それは「グローバリズムは(実質的に)悪である」って主張をする方々だ。
グローバリズムってのは、例えるなら、孤立していた町に道路が通って便利になったから、他の町と簡単に簡単に取引出来るようになりましたってことで、それ以上でもそれ以下でもない。
単純に技術の発達がそれを可能にしただけだ。
そして、そういう環境になったから、会社や工場や人やモノが安くで移動できるようになったので、自由に行き来するようになった、とそんだけの話だ。
そういう環境になってしまった結果、日本とアフリカのZ国の人件費が比較され、工場がアフリカのZ国に移転する…これは防ぎようがない。サポートがインターネット電話で中国の奥地に行くのもしょうがない。
もちろん僕とインドのゲームデザイナーが比較されるのもしょうがない。
そういう世界で僕らは生きている。
そしてこの世界を「昔の世界と比べて気に入らない」と言ってもしょうがない。既にインターネットがあり、通信コストは低く、情報が瞬時に世界を自由に行き来するのを逆戻りさせるわけには行かない。
「気に入らない、国は俺達を守れ」と主張するのは簡単だけど、それを実現しようとしたら、さきほどの例えを使うなら、道路にバリケード置いて「欲しいもの以外は通さない」って方法を取るしかないと思う。
だけど、こっちは道路を好き放題に使って外にモノ出すけど、外のモノや人はこっちにはいれません、って話が通じるわけもないのは明らかだ。それをやったら外の人が怒るに決まってる。
ならば、多分完全に封鎖する以外方法はなくて…もちろん、そんなことは出来やしない。
できもしない理想論(ついでに書くと、僕はそれを理想と思っていない)を主張するのは、全く意味はない。
それよりは、前回も書いたけれど世界中のどこでもご飯を食べられるように努力するのを助けてくれる国、ってのを目標にするほうがマシなのではなかろうか、と思っているのだった。
僕が結構尊敬している論客の方々はグローバルリズムについての立場はイロイロなのだけど、その中でどうにも納得が行かない主張をなさる方々がおられる。それは「グローバリズムは(実質的に)悪である」って主張をする方々だ。
グローバリズムってのは、例えるなら、孤立していた町に道路が通って便利になったから、他の町と簡単に簡単に取引出来るようになりましたってことで、それ以上でもそれ以下でもない。
単純に技術の発達がそれを可能にしただけだ。
そして、そういう環境になったから、会社や工場や人やモノが安くで移動できるようになったので、自由に行き来するようになった、とそんだけの話だ。
そういう環境になってしまった結果、日本とアフリカのZ国の人件費が比較され、工場がアフリカのZ国に移転する…これは防ぎようがない。サポートがインターネット電話で中国の奥地に行くのもしょうがない。
もちろん僕とインドのゲームデザイナーが比較されるのもしょうがない。
そういう世界で僕らは生きている。
そしてこの世界を「昔の世界と比べて気に入らない」と言ってもしょうがない。既にインターネットがあり、通信コストは低く、情報が瞬時に世界を自由に行き来するのを逆戻りさせるわけには行かない。
「気に入らない、国は俺達を守れ」と主張するのは簡単だけど、それを実現しようとしたら、さきほどの例えを使うなら、道路にバリケード置いて「欲しいもの以外は通さない」って方法を取るしかないと思う。
だけど、こっちは道路を好き放題に使って外にモノ出すけど、外のモノや人はこっちにはいれません、って話が通じるわけもないのは明らかだ。それをやったら外の人が怒るに決まってる。
ならば、多分完全に封鎖する以外方法はなくて…もちろん、そんなことは出来やしない。
できもしない理想論(ついでに書くと、僕はそれを理想と思っていない)を主張するのは、全く意味はない。
それよりは、前回も書いたけれど世界中のどこでもご飯を食べられるように努力するのを助けてくれる国、ってのを目標にするほうがマシなのではなかろうか、と思っているのだった。
2014-01-18 Sat [ レビュー::ゲーム ]
FF10の話を書くシリーズの第4回。
シリーズは以下。
■ FF10の話(1) - それは1991年から始まった
■ FF10の話(2) - ヘラクレスの栄光Ⅲの衝撃
■ FF10の話(3) - ファイナルファンタジーⅦ・その1
前回の最期で、『FFⅦ』こそが映像ドラマの手法でストーリーを語るゲームが完全に確立した瞬間だったのだけど『FFⅦ』にはもうひとつ特徴があった。
それはもともと三人称でストーリーを肩越しから見てる印象が強かったFFシリーズが、完全に三人称のスタイルを確立したということだ。
と、最後に書いたけれど、これを原理的なところから話を進めていきたい。
もともとRPGが登場した時、どんなゲームかを説明する言葉として「自分が主人公になって冒険できるゴッコ」というような表現をされることが多かった。
言い換えるなら「プレイヤーがそのまま映画とかの主人公になれるゲーム」。この説明はとてもわかりやすくて、受け入れやすいものだった。
だから初期のRPGでは「プレイヤーキャラクタが喋らない」のがいいとされていた。
プレイヤーがそこにいるのだから、プレイヤーの意思にそぐわない何かをしゃべらない…というわけだ。
そして今でも「RPGってのはなあ」と、この伝統的なオールドスタイルのRPG観をしたり顔で押し付けるゲーマーもいたりするわけだが、それはともかく、この伝統的なスタイルは、ストーリーが複雑になるに従って、イロイロ困ったことが起こる。
続きを読む▽
シリーズは以下。
■ FF10の話(1) - それは1991年から始まった
■ FF10の話(2) - ヘラクレスの栄光Ⅲの衝撃
■ FF10の話(3) - ファイナルファンタジーⅦ・その1
前回の最期で、『FFⅦ』こそが映像ドラマの手法でストーリーを語るゲームが完全に確立した瞬間だったのだけど『FFⅦ』にはもうひとつ特徴があった。
それはもともと三人称でストーリーを肩越しから見てる印象が強かったFFシリーズが、完全に三人称のスタイルを確立したということだ。
と、最後に書いたけれど、これを原理的なところから話を進めていきたい。
もともとRPGが登場した時、どんなゲームかを説明する言葉として「自分が主人公になって冒険できるゴッコ」というような表現をされることが多かった。
言い換えるなら「プレイヤーがそのまま映画とかの主人公になれるゲーム」。この説明はとてもわかりやすくて、受け入れやすいものだった。
だから初期のRPGでは「プレイヤーキャラクタが喋らない」のがいいとされていた。
プレイヤーがそこにいるのだから、プレイヤーの意思にそぐわない何かをしゃべらない…というわけだ。
そして今でも「RPGってのはなあ」と、この伝統的なオールドスタイルのRPG観をしたり顔で押し付けるゲーマーもいたりするわけだが、それはともかく、この伝統的なスタイルは、ストーリーが複雑になるに従って、イロイロ困ったことが起こる。
続きを読む▽
2014-01-16 Thu [ レビュー::ゲーム ]
FF10の話を書くシリーズの第3回。
シリーズは以下。
■ FF10の話(1) - それは1991年から始まった
■ FF10の話(2) - ヘラクレスの栄光Ⅲの衝撃
野島一成氏がスクウェアに入社した時は、スクウェアの大拡張期だった。
まず間違いなく『ヘラクレスの栄光Ⅲ』と『ヘラクレスの栄光Ⅳ』が評価されたのだと思うのだけど、まあそれはわからない。
そして、スクウェアで『バハムート・ラグーン』に関わったあと、あの『ファイナルファンタジーⅦ(FFⅦ)』にシナリオライターとして関わることになる。
さて…
『FFⅦ』は非常にいろいろな意味でゲームの歴史の中で象徴的かつ重要なタイトルだ。
まず第一に重要なのが、スクウェアが任天堂ハードではなく、PS1でファイナルファンタジーを出したこと。
1994年から始まっていた次世代ハード戦争と呼ばれていた熾烈な販売競争で、任天堂が主役でなくなったという象徴的な意味だ。
これももう20年近く前になって、この重要性がわからなくなってきている人がいると思うので、少し歴史的な説明を加えたい。
続きを読む▽
シリーズは以下。
■ FF10の話(1) - それは1991年から始まった
■ FF10の話(2) - ヘラクレスの栄光Ⅲの衝撃
野島一成氏がスクウェアに入社した時は、スクウェアの大拡張期だった。
まず間違いなく『ヘラクレスの栄光Ⅲ』と『ヘラクレスの栄光Ⅳ』が評価されたのだと思うのだけど、まあそれはわからない。
そして、スクウェアで『バハムート・ラグーン』に関わったあと、あの『ファイナルファンタジーⅦ(FFⅦ)』にシナリオライターとして関わることになる。
作品歴で見ると『バハムート・ラグーン』のあと『FFⅦ』ということになるのだけど、多分かなりオーバーラップしていると思われる。
さて…
『FFⅦ』は非常にいろいろな意味でゲームの歴史の中で象徴的かつ重要なタイトルだ。
まず第一に重要なのが、スクウェアが任天堂ハードではなく、PS1でファイナルファンタジーを出したこと。
1994年から始まっていた次世代ハード戦争と呼ばれていた熾烈な販売競争で、任天堂が主役でなくなったという象徴的な意味だ。
これももう20年近く前になって、この重要性がわからなくなってきている人がいると思うので、少し歴史的な説明を加えたい。
続きを読む▽
2014-01-12 Sun [ レビュー::ゲーム ]
FF10の話。第2回。
最初の話は以下。
■ FF10の話(1) - それは1991年から始まった
1991年当時、データイーストで『メタルマックス』を作っていた桝田さんから日記の話とかコマゴマと断片的に聞いてた、僕はワクワクしながら『ヘラクレスの栄光Ⅲ 神々の沈黙』のプレイを始めたわけだけど…
最初に書いておくと、ゲームの出来は相変わらずのDECOゲーだった。
操作性はヨロシクないし、バランスは変だし、グラフィックも素晴らしいとは言いがたい。
だけど、そんなことは僕にはどうでも良かった…というとウソになる。
気になった。ものすごくイロイロ気になった。
SFCのRPGとして見た時、既に『FFⅣ』が発売された後のRPGとしてみると、かなり微妙な出来だったと思う。
SFCは画面モードが複雑な上に、いろいろ扱いづらくて、めんどくさいことが多かったので、当時(1992初頭)のノウハウでは厳しかったのはわかるけれど、それでも高い質のグラフィックやプログラム…とは言いかねるのも事実だった。
ゲームシステム・マップ・モンスター・何をとっても微妙な出来と言わざるを得なかった。
特にバランスは問題がかなりあったし、戦闘の速度が微妙に遅いのと相まって、かなりイラっとするゲームだった。
でも、そういった様々な欠陥を乗り越えて、あまりある面白さがシナリオにあった。
とにかくシナリオが強烈で衝撃的だったのだけど、どこかでうまくリメイクされるチャンスがあったときの驚きと感動が残っていてほしいので、ここではネタバレは避けつつ、なぜ衝撃的だったのかについて、書いていきたい。
続きを読む▽
最初の話は以下。
■ FF10の話(1) - それは1991年から始まった
1991年当時、データイーストで『メタルマックス』を作っていた桝田さんから日記の話とかコマゴマと断片的に聞いてた、僕はワクワクしながら『ヘラクレスの栄光Ⅲ 神々の沈黙』のプレイを始めたわけだけど…
最初に書いておくと、ゲームの出来は相変わらずのDECOゲーだった。
操作性はヨロシクないし、バランスは変だし、グラフィックも素晴らしいとは言いがたい。
だけど、そんなことは僕にはどうでも良かった…というとウソになる。
気になった。ものすごくイロイロ気になった。
SFCのRPGとして見た時、既に『FFⅣ』が発売された後のRPGとしてみると、かなり微妙な出来だったと思う。
SFCは画面モードが複雑な上に、いろいろ扱いづらくて、めんどくさいことが多かったので、当時(1992初頭)のノウハウでは厳しかったのはわかるけれど、それでも高い質のグラフィックやプログラム…とは言いかねるのも事実だった。
ゲームシステム・マップ・モンスター・何をとっても微妙な出来と言わざるを得なかった。
特にバランスは問題がかなりあったし、戦闘の速度が微妙に遅いのと相まって、かなりイラっとするゲームだった。
でも、そういった様々な欠陥を乗り越えて、あまりある面白さがシナリオにあった。
とにかくシナリオが強烈で衝撃的だったのだけど、どこかでうまくリメイクされるチャンスがあったときの驚きと感動が残っていてほしいので、ここではネタバレは避けつつ、なぜ衝撃的だったのかについて、書いていきたい。
続きを読む▽